今回も、判断推理の対応問題の解き方について解説していきます!
この記事では、初めての方向けに丁寧に詳しくかつわかりやすく説明していきます。
例題も載せていきますので、一緒に解いて判断推理マスターを目指していきましょう!!
対応問題とは??
前回の記事でも説明しましたが、対応問題について、今回は詳しく説明していこうかな思います。
対応問題とは、人・物・場所・時間などが組み合わさって、「誰がどれに当てはまるか」を推理する問題です。
言葉では分かりにくいと思いますが、問題を解いていくうちに、「こんな問題か!!」と分かるようになります!
これから例題を載せながら、解き方の解説をしていきますので、よくわからない人でもご安心してください!!
対応問題の解き方について
実際に例題を解きながら、解説していきます。
解き方は以下の方法です
1 対応表を作る
2 条件を1つずつ表に反映していく
3 反映された情報を元に、条件を守りながら、分かることを表に記入していく(繰り返し行う)
この3ステップです。
実際に例題を解いていきましょう!!!
例題1 基礎問題
3人の学生A、B、Cはそれぞれ異なる通学手段(徒歩・自転車・バス)で通っています。以下のことがわかっている時、それぞれの通学手段何か??
①Aは徒歩で通学している。
②バスで通っているのはCではない
③自転車通学はBではない
〜解き方解説〜
ステップ1 まずは表を作りましょう!
| 徒歩 | 自転車 | バス | |
| A | |||
| B | |||
| C |
ステップ2 分かる情報を表に反映させていく!
| 徒歩 | 自転車 | バス | |
| A | ○ ① | ||
| B | X ③ | ||
| C | X ② |
このようになります。
ステップ3 反映させた情報を元に、条件を守りながら、分かることを記入していく
今回の条件は、問題文中の「それぞれが異なる通学手段」を使っているということです。
①徒歩がAとわかっているため、B及びCは徒歩ではない
| 徒歩 | 自転車 | バス | |
| A | ○ | ||
| B | ❌ | X | |
| C | ❌ | X |
このような表になると思います。
今回は基礎的な問題のため、1回の考察で全ての学生の通学手段がわかると思いますが、難しい問題となると①のような考察を何度も繰り返し行うことになります!
最終的な表↓
| 徒歩 | 自転車 | バス | |
| A | ○ | X | X |
| B | X | X | ○ |
| C | X | ○ | X |
Aが徒歩、Bが自転車、Cがバスとなります。
まとめ
今回は、本当に基礎的な問題に触れていきました。
今後難しくなっていくと、表が複雑になったり、2つ作成しないといけなくなったりします。
情報が多くなっていっても、1つずつ考えていけば、必ず答えに辿り着きます!!
次回は難易度を上げた問題の解説をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします!!
これからも勉強を頑張っていきましょう💪

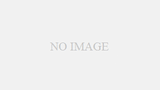
コメント